私は常日頃からお金の本質について考えています。私はお金に対する不安感がいつもあるからです。そんな矢先、先日、友人Aさんから心温まるエピソードを伺いました。それは、お墓参りの道中での老夫婦との出会いです。
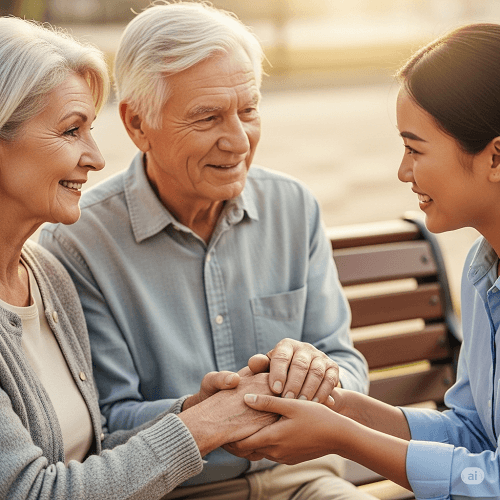
困っている人への差し伸べられた手
休日の霊園で、送迎バスが運休しているにもかかわらず、駅から1時間かけて歩いてきたという老夫婦。その姿を見たAさんは、純粋な善意から、帰りの駅まで車で送ることを申し出ました。対価を求めることなく差し伸べられた手は、疲労困憊していたであろう老夫婦にとって、どれほど心強いものだったでしょうか。
感謝の形としての2000円
駅に着き、別れ際に老夫婦が差し出したのは、2000円というお金でした。Aさんは当初受け取ることをためらったものの、最終的にそれを受け取ったそうです。
この2000円は、単なる金銭ではありません。それは、老夫婦が心から感じた感謝の気持ちを形にしたものであり、「この親切に対して何かお返しをしたい」という彼らの真摯な思いの表れです。Aさんがこれを受け取ったことは、老夫婦の「恩返しができた」という満足感を尊重し、彼らの気持ちを受け止めた、もう一つの親切だったと言えるでしょう。
お金が持つ「感謝」という側面
このエピソードは、私たちがお金の本質を考える上で非常に示唆に富んでいます。一般的に、お金は以下の3つの機能を持つとされています。
価値の尺度(Measure of Value): モノやサービスの価値を測る共通の物差し。
交換の媒体(Medium of Exchange): モノとモノの交換を円滑にする手段。
価値の貯蔵(Store of Value): 価値を将来に持ち越すことができる手段。
そして、これらの機能はすべて「信用」の上に成り立っていると説明されます。しかし、今回の老夫婦とのやり取りは、お金が「感謝の具現化」という、より人間的な側面も持ち合わせていることを教えてくれます。
老夫婦が差し出した2000円は、彼らがAさんに対して抱いた「ありがとう」の気持ちが具体的な形になったものでした。そして、Aさんがそれを受け取ったことで、感謝の気持ちが伝わり、両者の間に温かい善意の循環が生まれたのです。
「信用」と「社会的な合意」の先に
お金は、社会全体が「これは価値があるものだ」と共有する社会的な合意の上にも成り立っています。政府や中央銀行の信用があり、多くの人々がそれを共通の交換手段として認めるからこそ、私たちは安心してそれを受け取り、使うことができます。
しかし、その根底には、今回のエピソードのように、人々の間にある目に見えない「感謝」や「助け合い」といった感情が織り込まれているのではないでしょうか。老夫婦が感謝の気持ちを表すためにお金を選んだのも、それが現代社会で最も普遍的かつ受け入れられやすい「価値の交換手段」であり、同時に「気持ちを込める容器」でもあるからです。
まとめ:お金は人間関係を豊かにするツール
お金は、単なる経済的なツールとしてだけでなく、人々の感謝や親切といった感情を運び、社会における人間関係を円滑にし、豊かにする役割も果たしていると気づかされます。
今回のお墓参りでの出会いは、お金が単なる数字や紙切れではなく、人々の「感謝」や「信用」、そして「助け合い」という温かい心のやり取りを支える、人間らしいツールであることを改めて教えてくれました。

